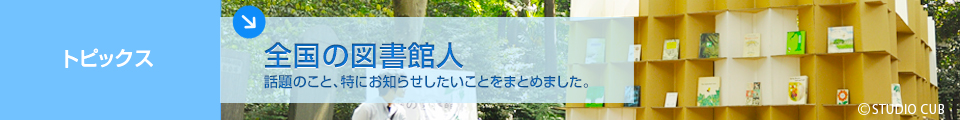【図書新聞連載】図書館に会いにゆく――出版界をつなぐ人々
配本に頼らない仕入本来の役割を愚直に追求
「1年やって評価が最低ならば交代することもある。『仕入れた以上は売り切る』というのはそういうことだ」
第19回(番外編)図書館流通センター・仕入部
毎週平均約1400点という膨大な数の新刊書籍がどのような経路を経て、図書館に届けられているのか――。これまでは、多くの図書館に書籍を納品する図書館流通センター(TRC)の図書装備の心臓部・新座ブックナリー、書籍の詳細な情報を付与したMARCを製作し読者と書籍の架け橋となっているTRC本社データ部の状況をレポートしてきた。本シリーズの最終回は、取引する図書館の目や耳となって出版社と書籍の仕入交渉をするTRC本社仕入部を直撃。仕入部長を務める田辺明彦氏に話を聞いた。
近刊情報を仕入れて発売前に商品を確保

仕入部の田辺明彦部長
東京・文京区の東京メトロ丸ノ内線の茗荷谷駅前にある図書館流通センター(TRC)本社ビルの4階に仕入部はある。所属する社員は16人。取引する取次は仕入れの9割を占める日本出版販売のほか、栗田出版販売、日教販、日本地図共販の3社。
仕入部の最大の仕事は、その名の通り、公共図書館や学校図書館に販売する「書籍の仕入れ」である。特徴的なのは、出版流通で言う「配本」(取次が書店に自動的に書籍を送品する仕組み)を受けていないことだ。30坪くらいの売場で品揃えにこだわる独立系書店では配本を受けずに独自に書籍を仕入れるケースがみられる。それは仕入れる書籍の物量が少ないからこそ可能な、特殊な事例である。一定以上の広さがある書店のほとんどは、「配本制度」と呼ばれる仕組みを通じて、その都度、書籍を納品してもらっているのが一般的だ。
だが、TRC仕入部はその物量の多さにもかかわらず、「配本」を受けずに、数百社もの出版社から日々、近刊情報(これから出る本の情報)を仕入れて、発売前に出版社へ注文して商品を確保している。それら商品は3つの専用システムに振り分けて、図書館に「新刊書籍」として案内される。この3つのシステムが「新刊急行ベル」「ストックブックス(SB)」「新継続」である。
既報の「新座ブックナリーの実態」(2月6日付)の記事でも少々触れたが、「新刊急行ベル」(通称・ベル)は発売後に入手が困難と予想される書籍を一定部数買い切って、図書館に定期的に送品する仕組み。実際には、図書館が資料費の予算の中から選書方針に基づいて決めた一定の年間購入額(冊数)をTRCと契約して、その予算額(冊)に合わせて送品する。例えば、年間購入額を60万円と設定した場合は、月々5万円程度に該当する書籍を送るというものだ。
その対象は、「文芸書」「児童書」「生活書」「教養書」「図書館」の5つのカテゴリーに相当する書籍。「図書館」は図書館の参考図書を整備する目的の「レファレンス」、図書館の管理運営等に関する書籍「ライブラリアン」という2つのグループに該当する書籍のカテゴリーを示す。
さらに、「文芸書」は「日本文芸書A」(岩波書店、角川書店、河出書房新社、講談社などの9社)、「日本文芸書B」(9社以外の出版社)、「外国文芸書C」(A、Bの出版社から刊行される外国文学)に、「児童書」は「児童読み物」「児童ノンフィクション」など3グループ、「生活書」は「くらしの実用書」「ビジネス・くらしの経済」など6グループといった具合に、5つのカテゴリーは合計30グループに細分化されている。
図書館はこれらのカテゴリーやグループごとに、自らにあったジャンルを選ぶことができる。これら30のカテゴリーを用意しているのが「スタンダードベル」、文芸書や児童書を中心にセレクトしたカテゴリーが対象となるものを「ハーフベル」と呼ぶ。
ベルは、言うなればTRCが図書館司書に代わって出版社の新刊書籍を発売前に確保する仕組みである。図書館には必備の書籍でありながら、出版界の独特な商慣習によって、発売後では必要部数を入手できない(しづらい)という過去があった。ベルは図書館の資料形成を支えていくために、それを克服したシステムとも言える。「以前に、『版元とTRCが売れ残った本を送りつけている』と言われたこともあった。しかし、第三者が選定した発売前の本を送っているので、その非難は当たらない」(田辺部長)。
ベル支える選書委員登録版元は231社

TRC本社4階の仕入部。
在庫の推移は毎日チェックし、追加などに対応
新刊書でも見当違いな書籍を図書館に送っていたのでは、この仕組みが何年も続き、さらに拡大していくはずもない。このシステムを担保しているのが、24人の委員で構成する「新刊情報による選書委員会(略称・新刊選書委員会)」(主催・図書館振興財団)という組織である。現役の図書館長や司書、大学教授など30~70歳代の専門家が集まり、仕入部が出版社から提供された近刊情報を基に、投票制で図書館に置くべき新刊書を選定している。
加えて、TRC社内の営業部や物流管理部、データ部など各部署にもベル委員を務める社員を設置している。これは、新刊選書委員会の役割を補うためのものだ。同点票の書籍が多数出た場合に限り、社員票を使って、それらの書籍を細かく順位付けしている。
出版社が「ベル」の仕組みに乗るにはベル版元としての登録(契約)が必要となる。現在協力社は231社。日本の主だった出版社は参加しているという。出版社231社の多くと毎月定例会を開催し、近刊情報などを中心に情報を交換。出版社が用意した近刊情報では書籍の内容がつかみにくい場合はゲラを要望するなど、未刊書籍の内容を補てんする情報を収集して、同委員会に提出している。
「加盟していただくのに、出版社の大小、歴史の長さ、人数の多寡は関係ない。図書館を大事にしていきたいというTRCの方針に賛同してもらえるか否か。以前に『契約しているのに、何故うちの書籍がベルに入らないのか』と言って、契約を止めた版元もあった。単に図書館に本を売りたいという認識だと、長続きはしない。ただ、これから『図書館のために』と考えてくれる出版社がいるのであれば、まずは私たちに近刊情報を提供してほしい。本が発刊されてからでは対応が難しい。また、取次に話をしたり、近刊情報のデータベースに登録したりすればいいと思っている版元が多いが、それでも私たちの目に届かないことが多い。図書館に確実に届けるために、できれば、見本出しのひと月前までに、直接仕入部にファックスでもメールでも情報提供いただければ、ベルへの選定やSBへの掲載について、仕入部内で必ず検討する」
SBは仕入の醍醐味 二重三重に部数確認
「ベル」に選ばれる票を得たものの、先述したグループに該当しない書籍や「ベル」から漏れたものは、「SB」と名付けられて、TRCの物流拠点・新座ブックナリーに10週間在庫される。期間中であれば図書館はいつでも商品を注文でき、確実に手元に届くというシステムだ。「SB」に選ばれる書籍は1週間で500~550点。ベルの登録はしていないが「SB」の登録をしている出版社の書籍・ムックが主な対象となる。
この「SB」は、仕入部からすると「仕入れの醍醐味が最も味わえる」と田辺部長は言う。
「出版社にSB用の書籍を発注する際は、これまで蓄積してきた2000週近い『新刊全点案内』のデータを基にして、類書やその著者の前作などを調べて傾向を掴む。そのうえで、これまで図書館との取引を通じて学んだ図書館の選書傾向、出版業界における知識や経験など、あらゆる観点から担当者が入荷部数を決める。さらに、仕入部の複数の目を通して、部決数を二重三重にチェックし、担当者が最終的な判断を下す」
図書館に送る書籍には、背ラベルの貼付やコーティングなどの装備を施す必要がある。そのため、新座ブックナリーにあらかじめ一定数の書籍を在庫しておかねばならない。その在庫がどれだけ出荷されたか、担当した書籍の販売数が毎週、成績表として示される。
「(新座ブックナリーを所管する)物流管理部の在庫推移は毎日追いかけている。『これは外してしまった』、『これは足りない』などの販売管理は怠らない。担当者の誰が足を引っ張って、誰がエースなのかは部内で共有するし、累計も出す。1年やって評価が最低ならば交代することもある。『仕入れた以上は売り切る』というのはそういうことだと思う」
1点1点を需要予測 返品率は5~8%に
さらに、TRCでは新刊書籍が発売から5カ月を経過した時点で既刊書扱いとなる。そのタイミングで一度、それら書籍の販売データをすべて出版社に提出する。その時点における返品率は10.5~10.6%という低さ。取次への年間返品率は5~8%の間(売行き良好書は既刊として販売し続けるため)ともいう。基本的に返品が少ないという特長ゆえに、売れ筋を含めた、初版部数が限られた「書籍」を発売前に満数確保することができるのだ。
このように「配本制度」に頼らずに、1点1点の書籍の需要を自ら予測して出版社に注文し責任を持って販売する姿勢に、出版業界は学ぶところが多いのではないか。当然、図書館市場の限られたマーケットという特徴はある。だが、商品を知らずに商いをすることは商売の根本にもとる行為。出版社は何を売りたいか、お客さんは何を欲しているのか、その両者をマッチングさせる小売の根本を仕入部は愚直に追求している。
専用システム最後の3番手「新継続」はシリーズものなどを自動的に送品するシステム。(1)年度ごとに刊行される白書や年鑑など、(2)文学全集などの定期刊行物、(3)文庫などのシリーズものの定期刊行物、(4)『地球の歩き方』のような不定期のシリーズ――を契約内容に基づいて配送する。
これまで見てきたとおり、新刊書の確保のイメージが強い仕入部だが、今年から3年かけて既刊書の大幅な再販促にも取り組んでいくという。アマゾンジャパンの「なか見!検索」のように、図書館専用の発注検索システム「TOOLi(ツールアイ)」では、試し読みサービスを搭載し始めた。「中身を確認したい」という図書館の要望に応える意味もあるが、既刊本の販売手段としても考えている。
「この『新刊全点案内』は年間50週にわたって、各図書館に送付している。その便に仕入部による企画提案書も同封している。その数、年間でおよそ200本。今は2月(取材時)なので、4月の企画『ゴールデンウィークを楽しむ』などをテーマに既刊書をまとめて提案している。出版社との定例会では新刊だけではなく、話題の既刊書などの話もしている。出版社との関係を密にしたうえで、図書館に喜んでもらえるような商材を探すのが私たちの仕事だ」
田辺部長は仕入部で20年以上の経験をもつベテランだが、同部に配属される前は、TRCの書店部が運営するアイブックスという書店の店長を務めていた。仕入部に移籍してすぐ、当時の図書館展示がNDC分類一本槍だったことに違和感を覚え、書店流に横断型の企画展示(書店でいうフェア)を提案し始めたのだという。
書籍の仕入に特化 医学書の売上急増
昨年、TRCではグループ会社も含めて仕入体制を変更し、ネット書店の「honto」の仕入は丸善ジュンク堂書店に、グループ会社の大学図書館や専門学校などの専門書をTRC仕入部が受け持つことになった。要は、コミックや写真集など図書館が扱わない商材は書店部門に任せ、専門書も含めた書籍全般の仕入に特化したのだ。それによって、この1年で「医学書」分野の売上が飛躍的に伸びたという。
「専門書は、図書館では購入しないと思っていた。しかし、それは錯覚だった。大学生が読むレベルの専門書であれば、図書館でも十分に購入対象になりうる。あるいは病院のそばに図書館があれば、患者やその家族が図書館を利用し、医学書を必要とすることになる。図書館から『こういう専門書を待っていた』と言われて、初めて気が付いた。これまでは、書店も図書館も『家庭の医学』書レベルの本しかないところが多かったのだ。書籍をきっちり売っていくという姿勢に変更したのは正解だった。今、出版流通は過渡期にきている。だが、私たちがやっているように、書店の方々も仕事の仕方が変化していくのではないだろうか」
掲載:2016.03.16