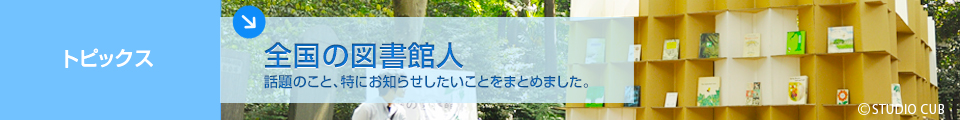【図書新聞連載】図書館に会いにゆく――出版界をつなぐ人々
学校司書ってどんな存在?
学校図書館の現状と課題~増える公共図書館と小中学校の連携
第12回 小石川図書館(東京・文京区)・山田万知代館長、学校支援統括・白木順子氏
2014年、改正学校図書館法案が国会で成立し、「学校司書」の立場が法律で位置づけられた。新設された第六条では、努力義務ながらも、学校には学校図書館の職務に従事する職員「学校司書」の設置、さらに国と地方公共団体には学校司書の資質の向上を図るための研修などの措置を講じるよう求めている。今年4月1日からは同法施行を受け、設置していなかった小中学校が学校司書導入の検討を始めるところが出てきた。また公共図書館から学校に司書を派遣する「学校支援」に取り組む自治体も増えている。東京都の文京区もそのひとつ。今年4月から区立の小中学校30校に対して、公共図書館から週4日、4時間、図書館司書の派遣を行うことになった。公共図書館5館(小石川・本駒込・目白台・湯島・大塚公園みどりの図書室)を指定管理者として運営している図書館流通センター(以下TRC)が15校、本郷・水道端・千石・根津図書室を運営しているヴィアックス・紀伊國屋書店共同事業体が15校を担当している。ここでは、TRCが担当する15校のうち5校に図書館司書を派遣している文京区立小石川図書館館長の山田万知代氏と、文京区でTRCが担当する15校の学校支援全体を統括する白木順子氏に、学校司書と学校図書館を取り巻く現状と課題などを聞いた。

山田館長(右)と学校支援統括の白木氏
学校司書の不在 制度の不備原因
――昨年の法改正の内容をきっかけに、全国には学校司書がおらず、普段は鍵がかかっている学校図書館が少なくないと知った。なぜそのような状況が続いているのか。
白木 学校図書館法では、12学級以上の学校には学校図書館の専門的職務を掌る「司書教諭」の必置が定められている。しかし、学校司書は以前の同法に明記されていなかったため、制度上、学校は学校司書を設置する必要はなかった。
――学校司書が不在の学校は、司書教諭が学校図書館を運営していたのか?
白木 司書教諭だけでは学校図書館の運営は難しい。司書教諭も他の教諭同様、担任をもち、多忙な業務を抱えている方がほとんどであるため、学校図書館に割ける時間はほとんどないのが現実だ。そのため、以前は「開かずの図書室」などと揶揄される状況が続いていた。それを見かねて、地域ボランティアやPTAが主体となって図書館を開館したり、蔵書を整理したりする地域もあった。
山田 司書を派遣している文京区では、司書教諭の先生が学校と司書のパイプ役になってくださっている。

礫川小学校で開催したお話し会
蔵書管理や授業支援 多事多端な学校司書
――自治体雇用の学校司書と民間から派遣される司書に違いはあるのか。
山田 学校に所属するか、公共図書館に所属するかの違いはあるが、業務内容は同じはず。学校図書館を整備し、蔵書を構築・整理し、利用促進・読書推進を行い、授業の関連資料を紹介したり、ブックトークを行う。子どもたちに一番近い図書館の担当者として、重要な仕事を担う。
ただ、学校に所属する学校司書は、校内に同じ立場の職員がいないため、相談や研修がしにくい場合がある。その点、文京区のように公共図書館から司書を出すと、学校に出勤する前後は公共図書館で勤務をするため、同じ立場の司書が集まり、相談がしやすい。レファレンスを受けても学校支援の司書同士、また公共図書館のスタッフとも情報交換ができるので、よりよい資料を持っていくことができる。学校支援統括の白木のような、担当地域全体を見渡す立場の人間が広い視野で学校図書館の相談にのることもできる。
――文京区の学校支援の業務内容は。
白木 文京区の場合、学校の意向で、勤務時間の詳細は異なるが、小学校は午前中から開館し、中休みと昼休みの利用時間における子どもへの対応、図書委員の貸出サポートを行うことが多い。中学校では放課後に開館できるように、時間を調整して開館しているところもある。いずれも学校側の要望に応じて対応している。
また、図書の時間という授業の一部を使って、読み聞かせやブックトーク、アニマシオン、ビブリオバトルなどを実施。新年度にはオリエンテーションとして、図書館の使い方や図書の分類法などを教える。これに加えて、授業のなかで図書館資料を活用していく授業支援も本格的に始まってきた。さらに、学校図書館に入れる選書・発注・受け入れ作業、「図書館だより」による情報発信、調べ学習の資料の準備、会議や研修、勉強会への参加などを行っている。
文京区の支援体制 週4日・4時間で
――週4日・4時間でそこまでの仕事をこなせるのか。
白木 業務を広げればいくらでも時間は必要になってくるが、もっと少ない時間で2校掛け持ちの地域もあるなか、文京区は恵まれていると思う。先生方や児童・生徒の読書環境や調べ学習への支援など、少しずつ結果を出し、自治体に相談しながら、今後さらによい形にしていきたい。
――そのなかで、学校支援統括の仕事は。
白木 小さいとはいえ、ひとりで図書館を運営し裏方の仕事を山ほど抱えているスタッフをフォローするのが学校支援統括の役割。それぞれの学校の特性や要望にあった学校支援ができているかをチェックし、課題や今後の目標をスタッフにアドバイスする。一人ひとりにあった研修や勉強の提案も行う。
また、公共図書館の利用者の方にも学校図書館のことを知っていただくために、小石川図書館内に担当する学校図書館の「図書館だより」の展示を行ったり、調べ学習の講座を企画したり、公共図書館と学校の間をつなぐ仕事もしている。これらはすべて文京区の中央図書館に定期的に報告し、困ったことは相談しながら進めている。
子どものために拡大しやすい仕組みづくりを
――自治体の直接雇用による学校司書の設置と指定管理者による学校支援について、体制上のメリット・デメリットはあるか。法改正を進めていた学校図書館議員連盟は学校図書館への派遣者は学校長の指揮監督下にないことを理由に学校司書に該当しないと判断しているが。
山田 私どもは指定管理者である公共図書館から学校へ図書館司書を派遣している形式をとっているため、文京区の中央図書館の指揮下ではあるが、それぞれの現場では学校長の指示にも従う。そこは双方にコミュニケーションをとりながらやっていけば問題ないのではないか。
最終的にはどのような雇用形態であろうと、司書が学校図書館で児童・生徒によい対応ができ、教諭と話し合いや相談の場がもて、研修制度もしっかりあって、という仕組みが、すべての学校に広がればよいと思っている。全国でも一部の地域では自治体直接雇用でそれが実現していると聞くが、しかし、ほかの地域に広がらなかった。
いま、目の前にいる児童・生徒に対して、前年よりもよい学校支援をやろうと取り組んでいるのが文京区。私たちは地域で働く民間企業として、文京区の考えに沿って、できるだけのことをしていく。学校支援に取り組む司書が少しでも働きやすい環境で長く働くことができるような仕組みづくりは、図書館の専門企業であるTRCとして必須と考えている。
将来的にはアメリカなみにレベルアップを
――学校司書の今後については。
白木 学校司書については何十年も不安定な立場であることは言われ続けてきたが、なかなか改善されなかった。それがようやく法律に明記されて、それだけでも一歩前進だと思う。司書の仕事によって、子どもたちがいまよりももっと本好きになって、調べたいことを自分の力で調べていけるような力をつけてくれることを願いながら、いま、仕事をしている。
法律には学校司書のレベルアップもうたわれている。将来はアメリカ型のスクールライブラリアン的な考え方に近くなっていくかもしれない。北米では、スクールライブラリアンはプロフェッサーの立場に位置付けられている。私の知り合いが46歳にしてスクールライブラリアンに合格したと喜んでいた。それだけ権威のある仕事だと市民に認められている。日本でもそうなっていくことを期待する。
掲載:2015.11.9