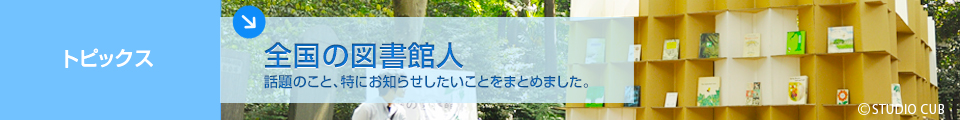【図書新聞連載】図書館に会いにゆく――出版界をつなぐ人々
失敗を恐れず、失敗から学べ。
どんなかたちでも夢は叶う
子育てをしながら3つの資格を取得し、館長に就任
第9回 福島県・喜多方市立図書館・佐藤由佳理館長
幼少の頃から本好きで小学生のときに司書の存在を知り、それ以来、図書館員を夢見てきた佐藤由佳理さんは、2013年4月、福島・喜多方市立図書館の館長に就任した。仙台の専門学校卒業後は民間企業に就職し、その後に結婚。4人の子どもの子育てに追われていた最中、ふたたび司書の夢が頭をもたげてきた。育児の傍ら、図書館流通センター(TRC)での短期アルバイトをきっかけに、図書館周辺の仕事に従事。通信制大学に入学し、大学卒業と同時に司書、学芸員、社会教育主事の資格を取得した。資格取得の念願がかなった佐藤館長は子育てと主婦の経験を活かして、「地域に密着し、問題解決できる敷居の低い図書館」を目指している。佐藤館長に話を聞いた。

佐藤由佳理館長
郷土文化把握し広く情報発信を
――100年以上の歴史がある喜多方市立図書館(1913年開設)は、2010年から指定管理者制度を導入し、TRCが運営を担当し始めた。その後、15年度「子どもの読書活動優秀実践校・図書館・個人」(文部科学省主催)の図書館部門で文部科学大臣表彰を受賞した。まずは佐藤館長に図書館運営について、どう考えているかを聞きたい。
「図書館は、いかに地域に密着して、情報を発信していくか、その一言に尽きる。それを実現する手段は様々ある。例えば喜多方は観光の街でもあるので、喜多方観光物産協会が認定する観光コンシェルジュという資格がある。当館のスタッフ7人(館長含む)のうち4人がこの資格を有している。観光客が図書館に立ち寄るため、地元の観光情報について応えられるよう、この資格を取得した。館内には市の観光交流課や商工会議所が配布するパンフレットなどを設置している。年に4回発行する『図書館だより』には観光コンシェルジュコーナーを作り、主な観光行事や文化財を掲載している。また、江戸時代に喜多方は、江戸、京都、伊勢白子と並ぶ日本四大染型紙の生産地だった。喜多方の知名度が低いため、昨年は会津型研究会の方に講師を依頼して座学を開き、今年は型紙のワークショップを企画した。さらに、『喜多方を漢字のまちにする会』と官民協働体として、まちおこしに関わっている。このプロジェクトの一環として、図書館でも漢字の講座を開催する予定だ。地元のことをきちんと把握していないと図書館の発展はない。郷土に特化した産業や文化は何か、そういう特色をきちんと把握し、表に情報発信していくことが大事だ」

官民協働し、漢字でまちおこし
――利用者層や貸出数などの状況は。
「利用者は、平日は主として40代後半より上の男女。土・日曜日は子ども連れの家族が多い。この地区は共働きが多いため、こうしたかたちになっている。貸出数は14年度末で13万2311冊」
――指定管理の導入から約5年。スタッフとも、その意識を共有し、地元密着はできているのか。
「喜多方市は指定管理の導入が比較的スムーズな地区だった。市内の美術館や体育館、そば資料館にも指定管理者が入っている。私は指定管理を受けてから2代目の館長となるが、当初からスタッフは地元の人を採用している。ただ、司書資格はあるものの、図書館員の経験がない者もいたので、そこは日々研鑽を重ねている。私は『自分たちの運営する図書館ではあるが、ここは預かり物。きちんと運営しないと自分たちの仕事場がなくなる』とスタッフによく言っている。そこを見誤ると、自治体との信頼関係もうまく築けない。選書して本を購入するのも信頼関係。仕様書というルールに基づいて常に情報共有をするなかで、信頼が生まれてくる。指定管理者制度をよく思っていない人から、TRCは会社の在庫品を選書して売っているなどと訳の分からない中傷を受けることもあるが、自治体と信頼関係を築いていれば、根拠のない話とすぐに理解してもらえる」
――図書装備のアルバイトから始まり、最終的には館長にまで上り詰めた。
「職場体験で、中学生や高校生が図書館に来る。そのなかには将来、司書になりたいという子もいる。そういう子にはいつも、『失敗を恐れず、失敗から学べ。夢を諦めたりしてはいけない。どんなかたちであっても夢は叶う』と言っている。私も小学生の頃から図書室にいて、本を読んでいた。司書の存在も知っていた。それが今の自分の原点だった。しかし、初めは司書になることができなかった。それでも、子育てをしながら資格を取って、TRCで図書館営業のアシスタントから入って、各地のエリアマネージャーなど図書館営業に携わってきた。そして、今の私がある。それは自分が諦めず、夢で終わらせないと思った結果である」
――女性の活躍の場を広げるためにも、図書館という仕事場は重要な意味を持つ。
「4人も子どもがいると、学校のPTAで様々な役職を引き受けることになる。これらの経験は、図書館イベントなどで活用している。また、地域の学校や教員とも密接に関わることになるので、こうした経験はまったく無駄ではない。むしろ、自分の子どものことなので積極的にかかわってほしい。地域で子育てや家庭に追われて、図書館員を諦めていた人、とくに女性にとっては、新しい道を拓くことができる仕事だと思う。ただし、図書館が接客業であることを忘れてはいけない」

喜多方図書館外観
――一部の出版社が図書館の貸出が本の販売を阻害していると指摘、発売から一定期間の貸出猶予を求めている。
「図書館は本の見本屋と思っている。個人で手に入れられない、高額なものなどは図書館で揃える。それが役割。私は、どうしても手元に置きたい本は購入している。販売と貸出を同じ土俵で議論するのは違和感があるし、こうした図書館の役割も理解してほしい。私たちは毎週、スタッフ全員で選書している。週の予算が決まっているため、選んだ本すべてを購入できない。購入できなかった本は検討ファイルにまとめ、定期的に司書全員の選書会議をひらき、購入の検討をしている。スタッフ6人が有資格だからこそ、資格に甘んじることなく、どれだけ学んでいるかを確認するためのものでもある。ただ、ひとつ懸念するのは、スタッフ全員が女性であること。男性目線の本がどうしても漏れてしまう。それが顕著に表れたのが、雑誌。婦人誌ばかりではなく、男性誌も入れてほしいと利用者アンケートでも要望があった。それで『週刊ダイヤモンド』や『歴史街道』などを今年度から入れた。いまは、バックナンバーがすべて貸出されるほど利用が多い」