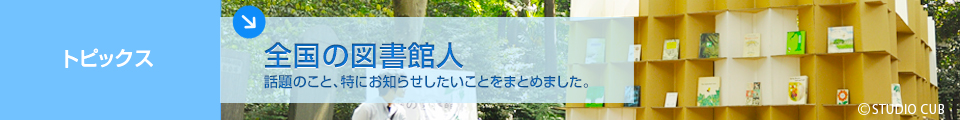【図書新聞連載】図書館に会いにゆく――出版界をつなぐ人々
「ご近所図書館」の実現に向け地域連携を深化
小中学6校の図書室を支援、団体貸出の定期便で教員の授業をサポート
第5回 練馬区立南田中図書館・正子敦司館長
2009年5月1日に開館した練馬区立南田中図書館(東京)は西武池袋線・練馬高野台駅から徒歩約10分の緑豊かで閑静な住宅街に位置する。児童館・敬老館に隣接するだけでなく、練馬区立南田中小学校の敷地に建設され、同校とも直結しているという全国でも珍しい公共図書館である。開館以来、小中学校6校の学校支援に取り組む一方、設立当時の基本構想である「ご近所図書館」を実現するために、地元で開催されるイベントには積極的に参加。図書を媒介にした地域連携を深めている。2代目館長として、同館を指揮する正子敦司氏にこれまでの取り組みを聞いた。(聞き手:図書新聞・諸山誠)
学校をサポート 貸出数が5倍に
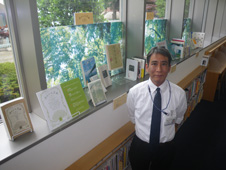
正子敦司館長
――南田中図書館は、練馬区立図書館として初の指定管理者制度の導入とともに、学校支援にも早い段階で取り組んできた。そのモデル事業対象校となった南田中小学校は2013年度子どもの読書活動優秀実践校として、文部科学大臣表彰も受けている。学校支援の現状とその成果は。
「練馬区の『学校支援モデル事業』として、開館当時から、南田中小学校ほか、5校の小中学校の学校支援に取り組んできている。南田中図書館は第2期(1期3年)に入って、現在も6校を支援している。同館での実践後は、練馬区内の指定管理者の増加にともなって、学校支援に取り組む区立図書館が徐々に増えていった。今では区内99の小中学校のうち、60校が公共図書館の学校支援を受けている。さらに、練馬区では図書館の学校支援に加えて、教育委員会による業務委託である学校図書館管理員の設置という2本立てで学校をサポートしていく体制を取っており、現状ほとんどの学校に支援が実施されている。学校支援の成果については、南田中小学校では、図書室の貸出数が5倍に増えたという話をうかがっており、どこも貸出数が伸びているようだ。また、年1回開かれる学校との連絡協議会の席でも、教員から一定の評価をいただいている」

独自に取材して作成した地域資料も展示
――具体的に学校支援とは。
「練馬区の場合、担当する小学校・中学校に専属の学校図書館支援員というスタッフを配置している。そのスタッフが担当する学校に年間100日、およそ1週間に2回訪問する。勤務時間は1日6時間。主な仕事は、学校図書室(館)の管理・運営の支援と教員のレファレンス対応。図書室(館)では図書の貸出・返却、企画展示のほか、読み聞かせやブックトークなどの授業支援もしている。教員のレファレンスに対しては、週1回の頻度で、団体貸出の図書を全校に送付・回収する配送便を設けている。各学年各教科で学ぶテーマに即した図書を、教員の要望に応じて迅速に貸出する仕組み。その要望を満たすために、南田中図書館では、調べ学習に役立つ資料5000冊を在庫する学校図書館支援書庫を設置している」
――学校支援によって学校図書室(館)は変わってきた。
「練馬区の例ではなく、一般的な話だが、毎年出る児童書の選定、さらにはどの図書を除籍にすればいいかという相談も多い。そういう点で我々がサポートする意味は大きいと思う。また、図書の背にラベルを張って、その分類ごとに並べるという基本的な整理も支援スタッフがいることで、よりスムーズにできる。さらに、管理面においては、学校図書室(館)の電算化という問題もある。南田中図書館担当のモデル事業対象6校は電算化することができたので、蔵書点検が1日でできるようになった。そうしていない学校は、1年に1回の蔵書点検も負担が大きいと聞いた。また、何が一番借りられているかという統計データを出すことも難しい。その一方で、電算化には導入予算や個人情報の取り扱い、パソコン操作などの運用面において慎重になる学校も多い。ただ、いずれは電算化の流れになるだろう」
井のいち文庫で地域店舗と連携
――学校支援以外の地域密着としては何を。
「今年で5年目となる練馬地域のクラフト市『井のいち』に『森の図書館』や『こもれびの庭 井のいち文庫』として参加している。いずれも、屋外に本を自由に読める空間を設置して読書を楽しむスペースを演出したもの。本は参加者が持ち寄った。この本は『井のいち文庫』として、自由に持って帰ることができる。読了後は感想を書き込んで、他の参加者の店舗に〝返却〟してもらうというルール。南田中図書館内にもその本を置いている。このほか、近隣の老人ホームの地域交流会でのリサイクルブックフェア、保育園などでのおはなし会なども実施している」
郷土資料を編さん 独自ブック地図も

芸術、医学、歴史関連の蔵書を手厚く収集
「2年前に近隣の図書館流通センター指定管理館である貫井図書館と大泉図書館と3館連携で『練馬ブックマップ』を作成し、利用者に配布している。区内102カ所の新刊書店や古書店、地域文庫、本を設置したカフェなどを掲載している。また、あしかけ2年で、地域史『団地のあるまち』を発行した。高度経済成長期に建設された近隣の南田中団地の周辺の状況を『まちの記憶』として残していくために、郷土史の研究家や区民学芸員の方に協力いただいて作成した。昭和から平成へ、姿を変えるこの地域の資料や記憶が失われていることに気付かされたとき、地域資料の収集・保存のために作成しようと思い立った。ほかにも、練馬区・石神井ゆかりの『照姫伝説』や『練馬の名族 豊島氏』を子ども向けに資料としてまとめた。こうした現存しない地域資料の編纂にも力を入れている」
「最近は『ミナミタナカ物語2015』というイベントを進めている。これは10代の目で見た南田中地域の情報誌をつくるというのが目的のプロジェクト。若い人の視点で町を再発見しようという試みだ。中高生に参加してもらいたいのだが、この世代は図書館から足が遠のきがちだ。だが、この世代は居場所を求めてもいる。中高生の皆さんが力を発揮できる機会を設けられればと思う」
――南田中図書館の蔵書の方針については。
「一般書や専門書に限らず、利用者のニーズに応じて揃えている。近くに順天堂大学医学部付属練馬病院があるので、医学物のニーズが高い。それと、土地柄なのか、写真集や芸術、音楽書などアート関連がよく借りられる。さらに定番ではあるが、歴史は強い。これに、環境関連を含めた資料の収集に力を入れている」
――一部の出版社から売上に影響するという理由で、図書館に貸出猶予を求めるという意見が上がっているが。
「図書館で本を借りたら、本を買わなくなるのだろうか。手元に置きたい本は買われるだろうし、欲しい本が何かというのも、本に親しんでいないと分からないのではないだろうか。私は図書館と本屋をはしごする。様々な形で本を読み、本に触れた上で、欲しい本を買うというのが今の購入のスタイルなのでは。だが、少し考えてほしい。もしも図書館がなくなったら、本を読むという習慣は今後も受け継がれていくのだろうか」