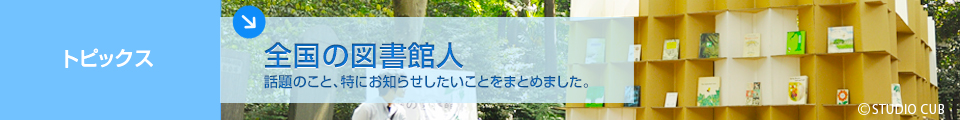【図書新聞連載】図書館に会いにゆく――出版界をつなぐ人々
生徒が本に目を輝かせる、そんな読書環境をつくっていかないと
学校図書館への司書委託、積極的な障害者雇用を率先して実践
第4回 真岡市立図書館(栃木県)・新井一郎館長
栃木県南東部に位置する真岡市は総人口約8万人の地方都市である。その市民の知の拠点となる真岡市立図書館は市民会館や市民公園、総合体育館など公共施設が集中する一角にある。現在の建物になって、すでに30年以上が経過。当時はモダンであったろう外観からは威厳が漂ってくる。
この館の主人である新井一郎館長は「受動型から能動型図書館に変えていく」を合言葉に、学校図書館への司書委託や公共図書館での障害者雇用など同県内でも珍しい取り組みを率先して実践している。新井館長に6年にわたる取り組みを聞いた。(聞き手:図書新聞・諸山誠)
館長室は不要 大胆に配置変え

新井一郎館長
――新井館長は2008年後半に、半導体製造装置の製造・販売会社を55歳で早期退職し、館長候補として図書館流通センター(TRC)に入社。09年4月から指定管理を受託した真岡市立図書館に赴任した。すでに指定管理2期目を迎えるが、受託した当初に取り組んだことは何か。
「まずは利用者が使いやすいように棚の配置など全体のレイアウトを変更した。とくに、カウンターの前は書架がギリギリまで配置されていたためスペースが狭く、利用者で混み合って非常に使いづらかった。また、低書架の上にびっしりと並べていた本を外して、他の書架に配列した。天井の蛍光灯の光が低書架の天板に反射しないため、館内が暗かったからだ。さらには館長室を撤廃してベビールームにした。というのも、女子トイレにベビーベッドはあったのだが、トイレの入口には扉がなかった。後にドアを設置して照明を明るくしたのだが、その当時はおむつを替えることはできても、授乳できる環境ではなかった。子育てする母親は図書館で育児の本を読みたいはず。そのための環境を整えたいと考え、ベビールームに変更した。館長室なんてものは必要ない。他にも、目の不自由な方のために、福祉室の拡大読書器を新型機に入れ替えたり、デイジー図書を充実させたりもした」
「探しづらい」で見出しを細分化

書架には3000枚の見出し
――館内の書架を見ると、文芸コーナーは著者別に配列するなど、各分野の棚が細かく分類されている。
「図書館アンケートで利用者からの改善・要望点で、『本が探しづらい』というのがダントツだった。そこで、図書の分類を示す背ラベル(請求記号)をすべて4ケタ化して、細かい見出しの陳列を実現した。3ケタのときは内科という分類で一緒くたにされていた図書が、4ケタ化することで、『消化器系』、『循環器系』と細分化して図書を配架することが可能になった。背ラベルの4ケタ化は人員・費用の面で多大な負担を強いられることが予想されていたが、東日本大震災の際の雇用対策である緊急雇用創出事業を活用することで実施の見通しがたった」
小学校5校を支援 プロ目線で”改革”
――14年には学校図書館法が改正され、学校司書の法制化が実現し、「学校は学校司書を置くように努めなければならない」と明記された。真岡図書館ではこれに先駆けて、公共図書館から司書を派遣して学校図書館の充実に取り組んでいる。
「一昨年の春頃から、調べ学習の導入による読書力等の向上などを目的に小学校への専任司書の配置について、真岡市の教育委員会・学校教育課の方と話していた。TRCはすでに埼玉・三郷市や東京・西東京市で実績があった。学校に派遣する司書を研修・教育する仕組みを整備していたことが決め手となって、昨年1月から市内の小学校5校でテスト運用を開始した。4月からは本格導入され、下野新聞の記事にもなったが、利用者も貸出数も2割増と成果を出した。ここで心がけたのは子どもたちが来たくなるような図書館づくり。ある学校図書館では、タテにつなげた2つの書架を分解して配置した。低学年の身長では書架の背が高すぎて利用しづらいからだ。また、薄暗い図書館の窓際に配置された書架の位置を変えて採光性を高めるなど、プロの目線で環境を整備した。さらに、企画コーナーやディスプレイを毎月変えるなど、子どもたちに興味を持ってもらえるように変化を持たせた。利用されない図書館は本もどんどん痛む。先生方と協力し、この負のスパイラルから抜け出していった」
――15年度の学校図書館との取り組みは。
「今年度も、予算の都合上で、引き続き5校で実施している。ただ、真岡市内の全18小学校の司書教諭や学校図書館に関わる教師が毎月1回、専任司書のいる学校とそうではない学校との差などについて情報共有するためのミーティングを開くようになった。現場の先生方のこうした動きは大きい。来年度の対象校拡大に期待が持てる。どの学校でも担任と学校図書館業務は兼務。しかし、担任業務の負担が重く、学校図書館にまで手が回らない。かといって学校図書館の専任者を置けないというのが現状だ。その一方で、調べ学習の広がりなどで学校も専任司書を置く必要性を理解している。その意味で公共図書館と連携した司書委託は今後も重要となってくるはずだ」

真岡市立図書館
知的障害の雇用 先入観捨てよ
――公共図書館としては珍しい、知的障害のある方を雇用されたと聞いた。
「知的障害者の栃木県立益子特別支援学校の生徒が一定期間、職業体験として真岡図書館に来る。それを受けたひとりの実習生が『図書館で働きたい』と希望を出してきた。自閉症を患っていたが、1年以上かけて、ご家族との面談から始まり、本格実習、図書館スタッフとの意見交換を経て、最終テストを実施し採用が決まった。公共施設では身体障害者の雇用には積極的でも知的障害の方にはそうではない。でも、それは先入観、固定観念にすぎない。今働いてもらっている方は非常に手先が器用で、本の修理やイベント用のポスター作成などの細かい作業が得意。もう3年も働いてもらっているが大きな問題になったことはない」
図書館通って本読む習慣を
――一部出版社が本の貸出猶予などを求めている。それについてどう考えるか。また、出版界と連携できることは。
「やはり、子どもの頃から図書館に通って、本を読むという習慣をつけることが大事。そういう人が減っているのと、出版界のマイナスは符合する。それはひとえに、大人が子どもたちの読書環境をつくってあげていないことに尽きる。このままいけば、本を読むのはごく一部となって、出版界だけでなく図書館も危うい。そこに対して歯止めをかけないと。ただ、中学校へ行ってブックトーク(図書館の本の紹介)をすると、生徒がすごく目を輝かせる。トークが終わっても、本を持って話し合っていた。毎月1回でも続けていけば本好きな子どもも出てくるはず。そのきっかけをつくるために、出版界も図書館もともに環境整備をすべき」