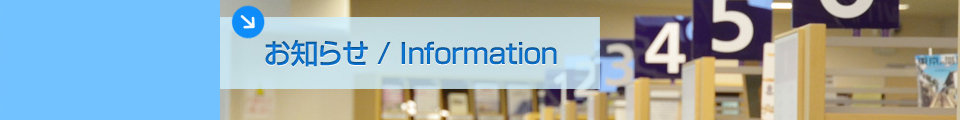第20回図書館総合展 フォーラム 複合館を中核としたまちづくり「学びの杜ののいちカレード」成功の秘密を探る! ―設計(デザイン)と運用(サービス)の融合―
日時:平成30年10月30日(水)10:00~11:30
場所:パシフィコ横浜アネックスホール 第2会場
主催:株式会社図書館流通センター
- 第1部:講演
-
- 『整備にかけた想い・市の活性化“カレード映像”放映』 粟 貴章(野々市市 市長)
- 『設計…運営との親和性の観点を交えて』 益子 一彦(三上建築事務所 代表取締役 所長)
- 『複合施設の運営 その多様性と市民の反応』 堀尾 あづみ(学びの杜ののいちカレード 館長)
- 第2部:パネルディスカッション「まちづくりの核に複合館が有効」
-
- 登壇者 粟 貴章(野々市市 市長)、益子 一彦(三上建築事務所 代表取締役 所長)、堀尾 あづみ(学びの杜ののいちカレード 館長)
- コーディネーター 野末 俊比古(青山学院大学 教授)
フォーラム会場内ではスマホやタブレットを使ったリアルタイム参加型ツールの「イマキク」を使用し、ご来場の皆様からご登壇のお三方に多くのご質問を頂戴しました。
当日ご回答しきれなかったものも含め、いただいたご質問について、登壇者からのご回答を掲載いたします。
質問・回答

質問)スタッフの人数と、勤務体制を教えてください。
回答)堀尾館長:2018年10月31日現在、館長1名とスタッフ24名在籍。早・中・遅番の3交代制です。質問)YAコーナーの使われ方は?勉強、友だちとのおしゃべり?
回答)堀尾館長:基本的には資料閲覧、学習です。質問)若い世代が主なターゲットになっていらっしゃるようですが、御高齢者の方の利用や反応はいかがでしょうか
回答)堀尾館長:年代によって利用に差があるとは感じられません。年配の方はおもに、新聞・雑誌コーナーや館内奥の比較的静かなスペースで読書されています。自動貸出機・返却機についても、問題なく使用されています。質問)夜間の利用状況は
回答)堀尾館長:17時頃から、利用者層が「高齢者・児童」→「学生・社会人」に様変わりします。利用人数は、週日・週末、天候・季節により異なりますが、閉館間際でも何十人かの利用者がいます。質問)おしゃべりオーケーとのことですが、運営上困ったことはありますか?
回答)堀尾館長:周囲の迷惑になるほどの私語(大きな声、複数人の話し声)や学習室での私語は注意することもありますが、基本的には問題なく運営しています。質問)従来の図書館のように静かに読書したいという声はありますか?(学習室では不便)
回答)堀尾館長:カレードは常に騒がしいわけではありません。平日昼間と夜間は非常に静かです。また、館内奥のエリア(南面一般フロア、北面閲覧席)は比較的静かなので、お一人でゆっくり読書されている方を多くお見かけします。利用者側で自分に最適な時間と空間を使い分けているように思います。質問)館内の飲食はどのようにかんがえていますか?
回答)堀尾館長:館内は蓋付きの飲料は持ち込み可能、食事はホワイエ(休憩コーナー)限定です。後者の違反については厳しく注意します。質問)運営してみて、施設をもう少しこうした方が良いなぁと感じるところはありますか?
回答)堀尾館長:旧図書館をほとんど利用しなかったYA世代が、カレードには大挙してやってきます。学習スペースがもう少し広ければ…と思うことはあります。質問)明るい図書館ですが本の日焼けとかは気にする司書の方はいませんでしたか?
回答)堀尾館長:フォーラム時にもお答えしましたが、季節や時間帯で日照場所が刻々と変化するので現場の人間は心配しておりません。仮に日焼けするほど動きのない(利用のない)資料があるなら、特集展示でPRするなど「陽のあたる場所」に出してやる必要がありそうです。
質問)南側の広場はどのように活用されていますでしょうか?
回答)堀尾館長:文字通り「憩いの広場」です。散歩、遊び場、ピクニックなど、市民が思い思いの形で利用しています。今後は主催イベントでも使用予定です。質問)堀尾さんに質問です。閲覧室から各スタジオに直接入るスタイルにデメリットはありませんか。騒がしくなるなど。
回答)堀尾館長:デメリットはありません。諸室出入りの音や匂いについて、現在のところ苦情はありません。メリットであれば、①図書館・スタジオの相互利用が見込める、②スタジオで主催イベントを実施できるので参加者を逃がさない(図書館にそのまま誘致できる)など、いくつか挙げられます。質問)配架の自動化はされていますか。予約本以外の図書の貸し出しは自動化されていますか。
回答)堀尾館長:資料の貸出・返却、予約資料の照会・引取り・貸出もすべて自動化です。一方、書庫も含め、配架は人力です。質問)dマガジンの閲覧サービスに興味があります。契約条件や経費などはどうなっているのでしょうか。
回答)堀尾館長:館内のWi-Fiをご利用のうえアプリをダウンロードしていただくと、雑誌約140誌が閲覧できます。10台同時接続が可能です。契約金額は月額5,000円(税抜き)です。質問)1年を待たずに来館者が50万人を超えたとのことですが、特別なPRやSNSの活用があれば教えてください。
回答)堀尾館長:現在の広報手段は次のとおりです。市域:市報・「カレード通信」(館内配布)、広域:HP、SNS(FB、Twitter)この他、地域のミニコミ誌やフリーペーパーに施設紹介やイベント情報を掲載していただくことがあるので、その効果が大きいと思われます。質問)月8回のイベントはスタッフにとって負担ではないですか?
回答)堀尾館長:月8回実施している「おはなし会」は、スタッフ担当回は3回のみで、残り5回はボランティアの方に運営をお任せしています。おはなし会に限らず、スタッフはどのイベントも前向き・自主的に取り組んでいます。質問)現在図書館へ足を運んでいない、或いは図書館へ行けない人たちへのサービスは、今後、どのようにしていかれるつもりなのかお聞かせください。
回答)堀尾館長:来館困難の利用者に対しては、旧図書館のサービスを継続し、市内4公民館と3施設に配本を行っています。また、「ののいち電子図書館」もアウトリーチサービスの一環として導入・運営しています。非利用者に対しての働きかけは現在模索中です。質問)良く運用を市民とともにやられてるがボケ防止的な取り組みを何か考えてますか?
回答)堀尾館長:折りしも、「図書館利用が健康寿命を延ばす」という趣旨の番組がテレビ放映されました。知的好奇心と他人との交流意欲のある人が図書館利用者です。その意味で、来館する行為自体が老化抑制と言えるのではないでしょうか。質問)学校図書館との連携について教えてください。
回答)堀尾館長:旧図書館からの継続で、毎月1回、市内小・中・高校の学校司書と図書館の合同会議を行っています。また、事務室に学校支援用資料を約1,100冊所蔵し、学校司書の要望に応じて貸出します。その他、「調べる学習コンクール」の実施や社会見学受入などで相互協力を行っています。
質問)学生の利用も多いようですが、地元の大学との協働、連携は?
回答)堀尾館長:市内にある金沢工業大学は以前より野々市市行政と観光・産業面で連携しています。その関連で、図書館も協働を行っています。具体的には、金工大「夢考房」(有志学生運営のものづくりプロジェクト)によるカレードの大型模型製作、大学の授業・ゼミで実施するアンケート収集場所提供などです。質問)横浜市の中学校は学校配置が進んでいますが、地域図書館との協働が進んでいない気がします。野々市市の取り組み教えてください。
回答)粟市長:月例司書連絡会や、学校図書館連絡車の運行等の学校支援サービスは、直面する課題解決のために、現場から生み出されたアイデアです。市立図書館側から、学校司書や学校教育課職員等、関係者に根気よく説明を続け、実施にこぎ着け、改良してきました。学校図書館と地域図書館との協働は簡単ではありませんが、できることから少しずつ始めていくことが大切かと思います。質問)カレードのスタッフの方は、図書館も生涯学習施設で分担はあるのでしょうか。 またスタッフの方は地元の方なども多いのでしょうか。
回答)堀尾館長:図書館と市民学習センターの各専門業務によって担当は分かれていますが(選書は図書館、展覧会企画は市民学習センターなど)、カウンターと電話応対の業務は共通です。全スタッフが図書館業務と市民学習センター諸室予約業務を行います。また、スタッフはほぼ地元採用です。質問)市民協働で図書館づくりをされているとのことですが、もともとボランティア活動が活発な地域でしたか?もし、そうでないならどのように市民を巻き込んだ活動をされましたか?
回答)粟市長:進んでいたとまでは言えませんが、市民協働に関する学習の場を設けたり、「市民協働によるまちづくり推進指針」や「まちづくり基本条例」の策定に市民が大きく関わったりして、ボランティアが活躍しやすい土壌づくりを進めてきました。
回答)堀尾館長:旧図書館のボランティアは、読み聞かせを中心とした活動を行っていましたが、カレード開館後は配架・書架整理、本の修理、イベントサポートなど、活動の場が増えました。サポーター募集に際し特別な募集方法をとったわけではありませんが、結果的には40名の増員になりました。「新しい図書館で何かやりたい!」という市民の意欲の賜物と感謝しています。質問)図書館サポーターの養成講座の育成には講師を頼むのでしょうか?その場合の講師料は?運営は誰が中心になるのでしょうか?
回答)堀尾館長:講師選択も含め、講座運営はカレードのサポーター担当スタッフが行います。今年度の講師は県立図書館職員や県内大学教授に依頼しました。講師料はカレードが負担します。質問)堀尾さんにご質問です。主催講座の話がありましたが、講座の中で図書館の資料を活用したことで、学びが深まった、というような事例があれば教えてください。また、今後企画していらっしゃる講座があれば教えてください。
回答)堀尾館長:諸室周囲に配架している関連資料がお役に立っているようです。例えば陶芸教室では、講座中は図案集を参考のため部屋に持ち込んで皆さんでまわし読みしたり、講座終了後は自宅での楽しみとしてやきもの関係の本をお借りになったりします。料理教室もしかりです。
質問)複合施設の決定プロセスを教えていただけますか。
回答)粟市長:旧図書館は老朽化に加え、面積、蔵書数が5万人都市の図書館としては満足できるものではありませんでした。更に、生涯学習活動においては、市民や児童生徒の文化・芸術活動を支援する施設の不足が課題となっていました。市民、関係団体、有識者らで構成する「検討委員会」で施設の基本構想を検討していただき、新図書館と市民学習センターの機能を一体とした複合施設化が実現したところです。質問)
・運営側と設計側との打ち合わせについて、いつ頃から、頻度や進め方はどうされたのか?
・設計から建築と運営までどのくらいの期間がかかりましたか?設計は市と設計会社さん、TRCさん、他にコンサルが入っているのでしょうか?
回答)粟市長:事業者選定の段階で、設計、建設、運営、管理それぞれの企業相互のコミュニケーションが図られたうえでの施設提案が得られていることが、PFI方式の利点であるとも考えております。そのため、設計期間が約1年間、建設期間が約1年間、開業準備期間が約3箇月と比較的短い期間で開館することができたと思います。具体的な設計協議は、設計、建設、運営、管理のそれぞれの企業と市及びPFIにおける市のアドバイザーのコンサルタント企業が同席した定例の会議を月1回から2回の頻度で開催してきました。質問)図書館と市民学習の各機能の規模設定はどう考えたのか?また、それが利用者にどのような効果をもたらしたか?
回答)益子所長:市民学習の各スペースの収容人員と使い方とコストの側面から規模を設定しました。開架スペースはそこへの動線を加味してゆったりと設定しています。結果的に、一定の密度感を生み、施設全体の一体感ができていると思いますし、移動の混雑等は生じないようになっていると思います。
回答)堀尾館長:図書館と諸室の収容能力は、野々市市の人口規模に比してちょうど良かったのではないかと感じます。質問)益子先生の質問です。今回の図書館は、ゆうき図書館の発展形と思いました。
回答)益子所長:貴見のような見方をして頂いたことを、有り難く思います。結城は私が図書館建築を考えるうえでの立脚点です。その意味では当然発展形となると思います。質問)天井の素材は何でしょうか?光輝いているので。
回答)益子所長:厚1.2ステンレス♯400と厚1.2ガルバリウム鋼板パンチング加工メタリック塗装の組み合わせです。ともに幅300㎜です。質問)騒がしい図書館になるのではないかと不安ではなかったですか?吸音とかしてるのですか?
回答)益子所長:図書館の内部空間を構成する上で「うちそとの景色」「自然光」「音環境」「温熱環境」等が極めて重要だと考えています。今回の場合も、当初よりそれらに配慮して設計をしています。景色としては「にぎやか」であるけれども、ノイズを拡散させないことを主眼に設計しています。
天井の穿孔加工したバルバリウム鋼板の背面にグラスウール(吸音材)を入れて吸音しています(天井の面積の半分は吸音面となっています)。床面のカーペットと併せて音源の近くで発生音を吸収し、かつ音の反射をなくして、反響が生じないようにしています。施工後の音響測定においても、良好な吸音性能を発揮する結果が出ています。このことは、音響特性を問題にする必要がない単純な吸音量のみの問題ですので、設計段階で課題にさえすれば解決できるものだと思います。
質問)通路の床が赤いのは天井との関係ですか?
回答)益子所長:発想は野々市の市の花である椿です。
来館者にインパクトのある空間とするために、レッドカーペットのようにあしらいました。質問)建物内のレイアウトを検討する際に、市民意見はどのように聞き、反映をさせたのでしょうか?
回答)益子所長:設計以前の基本計画段階で市民の意見が集約されていましたので、直接的に意見を伺う機会はありませんでした。質問)設計段階で市民や司書の方の意見をどのように取り入れていったか教えてください。
回答)益子所長:提案当初より運営サイドとコミュニケーションを採りながら設計を進めました。しかも、比較的早い段階でこうした前例の少ない空間を実現することで運営側と合意しました。そのため、設計側が運営側の意見を採り入れるよりも、むしろ開館時間や運営スタッフの一元化など運営サイドの積極的な工夫によって成立しているといえます。質問)開館に向けて運営面で一番調整に苦労した点は何ですか?
回答)堀尾館長:旧図書館と規模が大きく変わったので、新ユーザー層や数の予想が困難でした。業務の繁忙度や選書にあたってのニーズが読めずに苦労したのが思い起こされます。質問)市長様へお尋ねします。PFI手法で事業を進めてこられましたが、5万人規模の小規模自治体でPFIに取り組まれる上で苦労した点、同規模自治体で今後取り組もうと検討されている自治体にアドバイスを一つするとしたらどんなことでしょうか?
回答)粟市長:苦労した点は、県内にまだ事例が少なく、PFIに関心を寄せる地元企業が少ないと同時に、大手企業もまた関心を示しにくいことなどです。アドバイスとしては、少し背伸びしても、立派な施設を作るんだという「夢」を、市民に十分に説明していくことです。質問)市長にお聞きしたいと思います。この図書館をつくるにあたり、KPIは何か設定されてましたでしょうか?
回答)粟市長:成果指標として 「年間入館者数」、「図書カード登録者数」、「年間貸出冊数」を設定しています。質問)施設の整備に対して、反対意見を持つかたもおられたかと思いますが、何に対する反対意見・ネガティブな意見がみられたでしょうか?
回答)粟市長:施設整備そのものに対しての反対意見は、特にありません。市民にとって、待ち望まれての整備であったためと思われます。質問)コストの返済償還年数はどのくらい見込んでますか?
回答)粟市長:建設費用(起債)の償還期間は20年間を見込んでいます。質問)
・イニシャルコストとランニングコスト及び指定管理料について教えて下さい。
・建設費用、年間維持費、委託料は?
・敷地面積、延床面積、建設費、ランニングコストを教えてください。
回答)粟市長:建設費用は約31億円、ランニング費用及び指定管理料(年次図書購入費含む)は約3億円/年です。敷地面積は18,822㎡、延床面積は5,695㎡です。質問)指定管理期間は何年ですか。指定管理期間終了に対し、切り替え時の管理者に対するインセンティブなどはありますか。
回答)堀尾館長:契約期間は開館後11年5ヶ月、平成41年3月末日までです。質問)パンフレットに、建築主がまちづくり会社になっていますが、特に資金面での 民間連携のスキームを教えてください。また、外観写真を見て、外の広場空間も魅力的に感じました。広場空間を市民の方がどのように使っているか教えてください。
回答)堀尾館長:資金は代表企業の采配により、適切に運用されています。「憩いの広場」の利用については、上記質問10をご参照ください。質問)指定管理料以外に、管理者が収益を得られている仕組みなどがあれば教えてください。
回答)堀尾館長:特にありません。質問)野々市市において多くの来館者数に恵まれている要因は何だと思いますか?
回答)粟市長:ゆとりある空間づくり、午後10時までの開館時間の長さ、自家用車やバスによるアクセスのしやすさ、図書館資料の豊富さ等、市民目線のサービスが高く評価いただけたと考えています。また、複合施設のメリットを生かして、民間事業者の柔軟な発想とノウハウを取り入れた数多くの催しを行ったことなどが考えられます。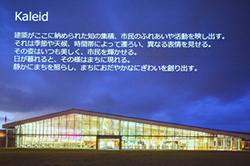
質問)「こうしておけばよかった」といった反省点はありますか
回答)粟市長:今の時点では、反省点は特にないと考えています。
回答)益子所長:建築は完成した時がベストな状態であるよりも、永くベターな状態を維持できることが重要だと考えています。したがって、建築だけなく図書館全体が常に新鮮な状態でいられるように見守っていきたいと思います。
回答)堀尾館長:特にありません。質問)デジタル書籍やインターネットの普及した時代に図書館はなぜ必要なのでしょうか?
回答)粟市長:これからの図書館には、図書を媒介として、ヒトやモノが集い、交流し、新たなコトづくりができる場としての機能が求められていると考えます。図書館のスタイルを時代とともに変えていくことが大切です。
回答)益子所長:いくつか考えられます。1.逆説的にいえば、多くの人が「図書館という居場所」を求めている。2.検索の手掛りを必要としない、視覚的かつ感覚的に総覧できる。3.無料のアミューズメント機能をもっている。4.ひとり自宅の自室よりも気分が良い。等々。
回答)堀尾館長:図書館資料のデジタル化や電子書籍の貸出が進む昨今、メディアの形態が図書館の存在価値・理由を左右しているのではないと考えます。どのような媒体が主流になっても人がリアルに集う場が社会には必要である、ということではないでしょうか。